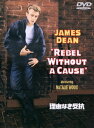初めて「老舗喫茶」という空間に足を運んだのは、高校生の頃だったと思う。
当時の私は低俗凡庸な日常風景を嫌悪し、梶井基次郎 の『檸檬 』の主人公の如く、連日街をそぞろ歩きしていた。その精神的苦痛に満ちた逃避行の顛末は前回の記事 で書いた通りだが、そんなアテもない徘徊の最中に、ある店に出逢った。
dilettantegenet.hatenablog.com
それは商店街を脇に逸れた、細い路地にぽつねんとあった。
店内は和洋の骨董 ( アンティー ク ) 箪笥 ( キャビネット ) 洋灯 ( ランプ ) セルロイド 人形が見下ろす先に、これまた大層な年代物である椅子と机が据えられていた。壁中に掛けられた古時計が、定時でもないのに鐘を鳴らしていた。珈琲を頼むと、必ずフランク・ロイド・ライト がデザインした「インペリアル カップ &ソーサー」に淹れられて出てきた。
制服姿で入るには、そこは少し敷居が高い場所ではあった。ましてや「コミュ障」だった自身にとって、店員と客の距離の近い空間でくつろぐことはなかなか難しく、どれだけ隅の席に座っても、丸めることのできない背筋にずっと緊張がわだかまっていた。
それでも日常に心休まる居場所を見出せなかった私にとって、そこは生まれて初めて、飢えた感性の空腹を満たせる空間だった。1杯500円の珈琲は、アルバイトもしていなかった当時の私にとっては決して安くはなかったけれど、少ない小遣いを工面して、私はそこに何度も何度も足を運んだ。
レジの奥の壁に、「百年たったら帰っておいで 百年たてばその意味わかる」 寺山修司 が書いたものだったと知るのは、もう少し後になってからだ。
数年前にその喫茶店 で撮って貰った写真。今も帰郷するたびに立ち寄っている。
店の名前は、2021年のロフトプラスワンWestトークショー ではお話したが、ここでは一先ず出さないでおく。ちょうど高校時に愛読していた嶽本野ばら 茶店 に通っていたことがあったらしい。つまりは名前を明かさずとも、多分、似たような魂の持ち主ならば、いつかはきっと辿り着く場所なのだろうと思っている。
その喫茶店 との出会いをきっかけに私は、いくら没趣味で醜悪な現実に辟易しようと、美しい喫茶店 は束の間の心の平穏を与えてくれるのだ、ということを覚えた。
年を重ねてのちに酒を嗜むようにもなったが、呑み屋が人生の精算場なら、さしずめ喫茶店 は人生の借入先と言えるだろう 。呑み屋では、酒精 ( アルコール 琥珀 色の酒で洗い流して空っぽになった魂の器に、今度は喫茶店 で珈琲色の ( ブラックな
「嗚呼こんな俗悪な世界で、いよいよ生きてゆかれない!」
そう心が悲鳴を上げるたび、古い喫茶店 に駆け込んでは人生を借り入れる。人々の物語が沁み込んだ茶けた壁に凭 ( もた 冥 ( くら
時折、そのカップ の中に、とぷんと入水自殺する夢を見る。
1983年創業、池袋「皇琲亭」にて。
そんなワケで、良い喫茶店 との出逢いは、良い金貸しとの出逢いと同じ意味合いを持つ 。
新しい街に出掛けるたびに、私は「○○(町名) +老舗喫茶」の文言で検索をかける。そうして出てきた店を、ひとつひとつGoogleマップ のリストに登録して、時に数軒ハシゴしながら少しずつ制覇していくことを、もう何年も続けている。これまでに訪れた喫茶店 をまとめてみると、そこそこの厚みがある本が出来そうだ。
それはちょうど、あちらで借りられなくなった人生を今度はこちらで借り入れているようなもの だ。ますます膨らむ生き恥という名の利子を始末しようと、多重債務をくり返して、気づけば借金地獄ならぬ借「生」地獄に陥っている。それは、生きることは骨が折れるが、死ぬことはもっと骨が折れるので、成仏できるまでは兎にも角にもまだまだ生きるしかないという地獄である。けれどまァ、普段からYouTube 上で自身の生誕を「堕獄」 と呼称しているように、この世はハナから地獄じゃわい、というのが私の見解であるから、これ以上地獄極まっても大した問題ではない。
借金を返すために借金をするというのは、かの内田百閒 大先生の偉大な教えでもある。貧者が金貸しを股に掛けるのなら、魂の窮民は老舗喫茶を渡り歩く 。私が推奨する多重債務法の良いところは、金を借りれば間貫一 ( はざまかんいち (『金色夜叉 』に登場する高利貸し) が冷酷に追いかけて来るけれども、喫茶店 で精力を借りても、何者にも追い立てられることがない点だ。せいぜい「嗚呼、今日も生きてしまった……」という自己陶酔 ( ナルシシズム (フリをする) のがオチである。
誰も彼も「金がない」とはよくボヤくが、「俗世の煩わしさに感性の泉が枯れ果てている!」と、そんなおセンチな嘆きも時にはしてみるべきじゃあないでしょうか。
「老舗喫茶」に必ず求めるワケではないけれど、あると嬉しいという、必要条件ではない十分条件 のようなものがある。
まずは30年以上の歴史があること 。肌感覚にすぎないが、90年代以降にできた喫茶店 と、80年代以前にできた喫茶店 では、何となく風格に違いがあるように感じている。特に「名曲喫茶 」や「ジャズ喫茶」と銘打たれた喫茶店 は、それが必要とされていた時代────まだ音楽がどこでも気軽に聴けなかった時代に開業したものが多いから、あまりハズレがない。勿論歴史があるからといって、代替わりしていたり、店内が改装されていたりして、趣がすっかり変わっていることもしばしばだけれど。
1970年創業、京都左京区 のジャズ喫茶「ヤマトヤ」にて。 2013年にリニューアルしたため店内は小綺麗だが、レコードの所蔵を見ればその歴史は一望できる。
次に店内にシノワズリ 趣味の調度品または磁器があること茶店 にはないが、そしてそんな店も勿論好きなのだが(「古い」というより「ボロい」喫茶店 にもそれはそれで矜持がある) 、カウンター奥に磁器コレクションを並べているような店ならば中国趣味は欠かせない。主観的な経験にすぎないが、いくらカップ &ソーサーに拘っていても、西洋モノしか置いていないところは、上辺だけレトロに小洒落ただけの店が多いような気がしている。外見だけでなく歴史の重みをも脈々と継いでいる店には、何故だかどこかに必ず、シノワズリ 趣味が覗いている。
1987年創業、千住宿 「珈琲物語」にて。
あとは煙草が吸えるかどうか 。自身が喫煙者である以上に、古色蒼然とした店内で燐寸 ( マッチ 紫煙 を燻らせる────その一連の動作とポーズが、私にとって、歪んだ魂を整えるための準備運動のようなものだからだ。それは隠者が瞑想に入る前に決まって行う所作に似る。立ちのぼる細い煙を微睡 ( まどろ ルサンチマン が溶けて消えていく様子を錯覚することがある。
昨今は米国の影響か日本でも禁煙運動が盛んで、時にヒステリーを疑うほどの拒絶反応を目撃することもあるが、それは「文化」は「健全」なものであるに違いなく、「健全」と「健康」は同義であり、「健康」であるためには「無害」を心がけねばならない 、と思い違いを重ねた人の主張 ( クレーム 茶店 では喫煙可能なのだから喫煙する……それくらいは流石にお見逃しいただきたい。
それをとやかく言われても、寿司屋に来て「何故魚の臭いがするのか!」と怒鳴り散らされているような矛盾を感じる。
1974年創業、沖縄那覇 「イシャラー」にて。
老舗喫茶を巡る利点は、実はもうひとつある。それは喫茶店 を探して街歩きができる 、いうことだ。知らない街に降り立った時は、先述の通り必ず「○○(町名) +老舗喫茶」で検索をかけ未踏の喫茶店 に向かうのだけれども、それまでの道中もなかなかロマンチックな刺激になることが多い。
ちなみに誤解のないよう先に書いておくが、あくまでこれは精神 ( メンタル 身体 ( フィジカル
かつては日本の街並みを心底軽蔑していた私も、例の耽美の師匠のお陰で、荒涼とした日常風景の中に隠れた美の地下水脈を見出すことができるようになり(第十書簡「我が師匠──或る耽美主義者の面影」 参照) 、何でもない光景はこれから何かを見つけ書き付けるためのまっさらな白地図 であると思えるようになった。そしてその地図には、老舗喫茶という名のオアシスが、すでに、確かに点々と記されている のである。
無風流なコンクリート 砂漠に、雑然とした都会のジャングルに、静かにクラシックの流れる、べっこう色の老舗喫茶がシンと佇んでいる様子を想像して欲しい。社会の野蛮なイザコザにいくら揉まれようと、自身にはいつでも立ち返って魂を労わることのできる喫茶店 がある────その安心感、至福は筆舌に尽くしがたい。
初めて降り立った街を楽しむためには、ただ一軒、貴方が優雅な心持ちになれる喫茶店 を探すだけで良いのだ。知らないことに大金を叩いたり、安い遊びしか詰まっていない商業施設に彷徨う必要は微塵も ない。浪漫ちっくな喫茶店 で束の間、茶を啜り、実りあるひと時を過ごすだけで、未知の土地は愛する既知の街になる。
もう大層な大人になったというのに、未だに幼児の意地っ張りの如く、スターバックス やドトール 、タリーズ といったチェーン店には頑なに行かないでいる(コメダ は粋と気概を感じるのでちょっと好き) 。別段それらを嫌悪しているワケではなく、自分は自分の好きな空間にできる限り金銭を落としたい、という単純 ( シンプル
消費行動は文化の支援に他ならない 。チェーン店ばかり使っていれば、街はコピー&ペーストしたような店舗でその内埋め尽くされるようになるだろうし、老舗喫茶を大いに利用していれば、都会の幻惑のオアシスは永遠に滅びることはないだろう。文化とは一朝一夕で出来るものではないはずだ。人々が毎日繰り返す僅かな、小さな取捨選択が少しずつ少しずつ蓄積して、徐々に大きな潮流 ( ブーム
稀にどうしても老舗喫茶が見つからなくて、原稿作業したさにチェーン系の喫茶店 で妥協することがある。すると効率の前に己の美学を穢した自身がどんどん情けなく恥ずかしく恨めしくなってゆき、3日は精神のどん底 を彷徨うことになる。
これをただの意固地だと笑う人もいるかもしれない。しかしそれは、文化の欠片もない粗末な日常に押し込まれ続ける息苦しさ を、世俗の煩わしさが日々魂を堕落させてゆく虚しさ を、美への切望と生きる切実さ を知らない人だろう。
私にとってチェーン店で妥協することは、野蛮草昧な現実に屈することと同義なのである。
1962年創業、恵比寿「喫茶 銀座」にて。
また一方で、「日々触れているものが少しずつ自分を形作っていく」とも思っている。この「外部要因から自分を整形していく」思考については、自身の苦い経験をもとに第九書簡「無個性の欺瞞」 に書いているので是非参照いただきたいが、「どう在るか」という内的なものから発露する言動以上に、「どういうものに囲まれているか」という外的な諸要素が、案外人間を形作るものだと私は思っている。
粗野な生活空間に埋もれていれば、何となく冴えない風貌になっていくだろうし、豊かな文化に触れていれば、どことなく潤った雰囲気が纏わっていくものだ。オーラと言い換えても良いが、そうしたスピリチュアル臭のする感覚的でしかない話以前に、些細な所作に、ほんのわずかな言葉遣いに、人の奥ゆかしさは覗いてくる。
それは決してお上品であるか否かという話ではない。品は良いが脳味噌は空っぽな空気人形のような人もいるし、品はなくても見識と機智で輝かんばかりのディオゲネス のような人もいる。その違いを説明していると貴方の珈琲がすっかり冷めてしまうだろうからここでは割愛しておくが、老舗喫茶通いは、どんな人でも手軽に摂取できる美しい「外部要因」だと思っている。
自身の生活空間を思い通りに演出しようとすると、スペースの問題、金銭の問題、ライフスタイルの問題……様々な障害が立ちふさがる。しかし老舗喫茶は、誰もが行くことができて、束の間、優雅な気分に浸ることのできるサロンだ。その豊かな時間を持つ人と持たない人では、形成される人格もまた異なってゆくのではないだろうか。
dilettantegenet.hatenablog.com
老舗喫茶で愛する誰かと逢引き ( ランデヴー 相まみえる ( ランデヴーする
そもそもフランス語由来のランデヴー rendez-vous という単語は、動詞 rendre(行く) の命令形 rendez (行け) と、人称代名詞 vous(貴方) が合体して rendez-vous
それは全くもって難しいことではない。私達はすでに、老舗喫茶という最も手軽で最も美しい選択肢を、このカップ &ソーサーの中に持っている。
ピエール=オーギュスト・ルノワール 《カフェにて》(1877)